お役立ち情報
【Webサイト制作】要件定義とは?進め方や必要項目を解説
良かったら”♥”を押してね!
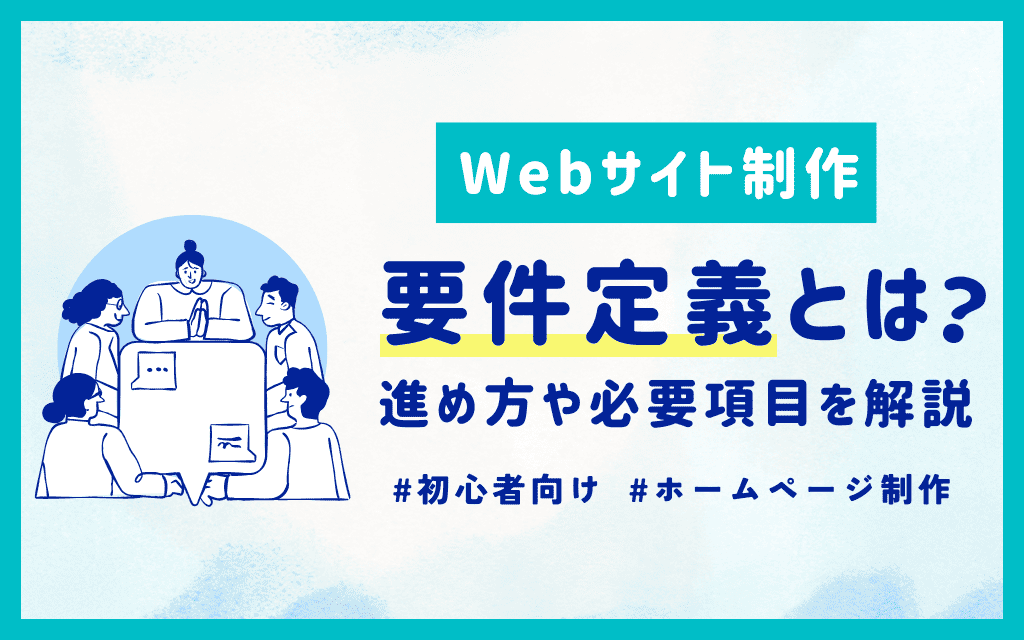
要件定義という言葉を、Webデザインなどの依頼をした時に聞いたことはありませんか?もしかしたら、よくわからずに任せっきりになっている方や、気にしたことのない方もいるかもしれません。
デザインの依頼をしている立場からすると「そんなもの必要なの?」「早くデザインを見せてほしい」と思ってしまいますよね。
しかし、プロジェクトを進めることにおいて、要件定義は両者共にとても重要です。今回は、Webサイト制作における要件定義について、簡単に分かりやすく解説していきます。
目次
Webサイトの要件定義とは?
Webサイトにおける要件定義とは、サイト等を制作したり、リニューアルしたりする際に、コンセプトや実装したい機能、スケジュールや予算といった条件や依頼内容などを集め、整理してまとめることです。
単にまとめるだけでなく最終的には「要件定義書」という形で可視化し、プロジェクトに関わる関係各所と共有します。ここでの関係各所とは、社内はもちろん、制作会社などの社外の関係者も含めます。
この要件定義を最初にきちんとおこなっておくことで、Webサイトを制作する目的や目標、制作に要する時間や費用がなどを可視化することができ、ゴールまでの道のりが明確になります。
大規模なWebサイト制作になればなるほど、目的や目標も複雑化しやすくなり、関係者も増えるため、制作の過程で各々の方向性がズレてしまったり、迷ってしまったり、実装すべき機能やレイアウトが漏れてしまったり・・・といったことが起こることがあります。
要件定義には、こうしたトラブルを軽減・防止する役割があります。
Webサイトの要件定義をおこなう場合は、「5W1H」というフレームワークを利用して状況を整理するのがおすすめです。5W1Hとは、ビジネスコミュニケーションの基本を示したフレームワークで、意識すべき6つの要素があります。
Webサイトの要件定義では、
- Webサイトを制作する側の視点
- Webサイトを利用するユーザー視点
についてまとめると整理しやすいです。
<例:Webサイトを制作する側の視点の場合>
| 5W1H | 整理する内容(例) |
|---|---|
| When(いつ) | いつまでにWebサイトを公開するのか/着手時期や期間/想定されるスケジュールなど |
| Where(どこで) | Webサイトをどこで制作するのか(例:社内 、制作会社など) |
| Who(誰が) | 誰がプロジェクトを管理するのか(例:工程ごとの担当者、チームのメンバーなど) |
| What(何を) | 何をできるようにしたいのか/どんな機能を実装するのか |
| Why(なぜ) | なぜWebサイトを制作するのかという、背景や目的、解決したい課題など |
| How(どのように) | どのようにサイトを制作するのか/使用するツールや開発言語、Webサイト公開後の運用などはどうするか |
<例:Webサイトを利用するユーザー視点の場合>
| 5W1H | 整理する内容(例) |
|---|---|
| When(いつ) | ユーザーがサイトを利用する時間やタイミングなど(例:通勤時、夜寝る前、…) |
| Where(どこで) | どういう環境でWebサイトを利用するのか(例:自宅、会社、など) |
| Who(誰が) | どんな人がWebサイトを利用するのか(ターゲット) |
| What(何を) | Webサイトを通じて、何を提供するのか(例:商品購入/採用情報など) |
| Why(なぜ) | ユーザーはなぜこのWebサイトを利用するのか(例:サイトの利用意図や、検索意図など) |
| How(どのように) | ユーザーはどのようにWebサイトを利用するのか(例:スマホ・PC・タブレットなど) |
Webサイト 要件定義の進め方
それでは、どのようにして要件定義を決めていくのでしょうか。全体としては以下のような流れになります。
- 現状の把握と課題の確認
- 仮説を立てて解決方法を決める
- 合意形成をする
- 要件定義書を作成する
順番に確認していきましょう。
現状の把握と課題の確認
まずは、現在抱えている問題や改善が必要な点をすべて集めます。これは文字通り、出せる限り全部あげましょう。
最初に課題を把握しておくことで、何から取り組むべきなのか、重きを置くべきポイントはどこにあるかなどを整理し、優先順位を付けることができます。
たとえばサイトリニューアルの場合であれば「サイトの動作が少し重い」「アクセス数が伸びない(SEOが弱い)」「モバイル版のレイアウトが欲しい」「Webサイトから商品を購入できるようにしたい」など、さまざまな課題が挙げられます。
また、新規でサイトを制作する場合は「会社の認知が広がらない」「サービスや採用情報に関するお問い合わせをWebで受けられていない」「企業のブランドイメージを構築できていない」など、コーポレートサイトがないことで感じている課題を明確にしていきます。
課題の洗い出しの具体的な手段としては、社内の担当者などにヒアリングを実施し、解決すべき課題や情報を整理する方法があります。社内へのヒアリングの他にも、アンケートなどを利用して顧客やエンドユーザーの意見を確認してみると、客観的な要望もふまえて方向性を整理しやすいです。既存サイトがある場合は、サイトのPV数や流入経路といった定量的なデータから分析をおこなうことも有効です。
その他、顧客やエンドユーザーから集めた情報をもとに、ペルソナを設定してみることも、社内での共通認識を得るために効果的な方法です。
■ペルソナってなに?と思った方へおすすめの記事
関連記事
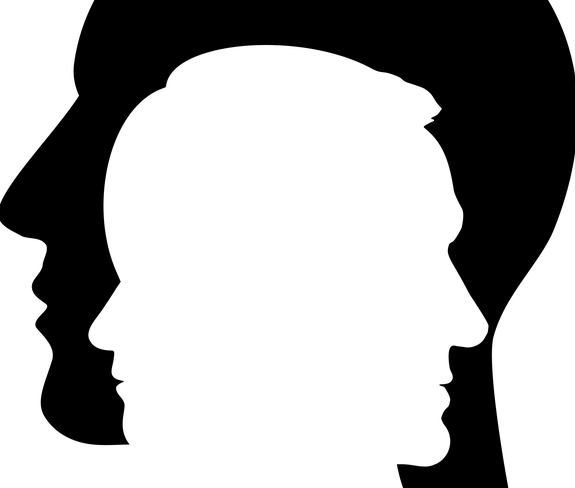
ペルソナ設定とは “ハズさない”Webマーケティングのコツ
課題を洗い出した後には、それらをカテゴリ分けして整理してみましょう。
たとえばWebサイト制作場合は、
- 目的
- UX/UI
- デザイン
- コンテンツ
- SEO
- 技術面/運用面
といったカテゴリで整理してみると分かりやすいです。
<例:カテゴリの整理>
| カテゴリ | 課題の内容(例) |
|---|---|
| 目的 | ・顧客に自社サービスが認知されていない ・問い合わせや売り上げにつながっていない |
| UX/UI | ・導線が分かりにくく、情報を見つけにくい ・ページの表示速度が遅い ・スマホで見ると、使いづらい |
| デザイン | ・デザインが古く、競合に比べて見劣りする ・ブランドイメージが伝わらない |
| コンテンツ | ・情報が古い(更新されていない) ・必要な情報が不足している ・自社の専門性を裏付ける情報がない |
| SEO | ・検索意図を考慮したページや記事がない ・内部リンク不足でクロール効率が悪い |
| 技術面/運用面 | ・CMSが使いづらく運用が属人化している ・サーバーの処理が遅い ・外部システムとの連携ができない |
カテゴリ間でも優先度が高いものや低いものがあるので、整理したあとは優先順位もつけていきましょう。
■UXってなに?と思った方へおすすめの記事
関連記事

UI(ユーザーインターフェース)とは? ~さまざまなインターフェースとその違い~
仮説を立てて解決方法を決める
次に、集めた情報をもとに課題のどこに原因があるか仮説を立て、どのような方法で解決をしていくかを決めていきます。
たとえば、既存サイトで「動作が重い」という場合には、サーバー負荷、非効率なコード、ネットワークの問題などさまざまな要因が考えられるので、どれが原因なのか仮説を立てて、必要に応じて検証しながら解決方法を決定します。
また、新しくWebサイトを制作する場合は、サイトに訪れたユーザーの行動を把握するために「カスタマージャーニーマップ」を作成してみるのもおすすめです。カスタマージャーニーマップとは、ユーザーがサービスや商品の購入に至るプロセスを時系列に記したシートのことです。
想定しているターゲットがWebサイトを利用した場合に、どういった感情を抱き、どのような行動をするのかを分析することで、サイト構築の方向性を整理しやすくなります。
検証を行う場合は、時間や人的リソースには限りがあるため、最初に整理した優先順位をもとに、優先度の高いものから着手していくのが良いでしょう。
また、制作会社などの外部の関係者とも連携し、解決方法が現実的に実装可能か、予算はどのくらいかかるのか、新たな問題は発生しないか、なども確認する必要があります。
■カスタマージャーニーマップって何?と思った方におすすめの記事
下記の「コンテンツマーケティングの始め方」でカスタマージャーニーの作成例をご紹介しています。
関連記事

【初心者向け】コンテンツマーケティングとは?
合意形成をする
次に、合意形成を行います。
合意形成とは、上記で決めた内容について関係各所の合意をとることです。ここでポイントは、共有・合意をとるのはWeb担当者だけではなく、関係のある部署の上長や上層部、そして外部の関係者からも合意・承認を得ることです。
この段階で関係者同士の意見の食い違いや認識の違いを確認しておくことで、後になって問題を再検討するリスクを軽減する効果が期待できます。また、関係各所が共通の目標を持ち、同じ熱量でプロジェクトに臨めるようにするためにも、こうしたコミュニケーションは重要になります。
要件定義書を作成する
最後に「要件定義書」を作成します。要件定義書とは、上記で定めた内容を書面にまとめることです。書面に残すことがとても重要になってきます。
要件定義書は一般的には専門知識や経験がある制作会社側(開発会社側)が作成します。場合によっては、制作会社と依頼者側が共同して作成することもあります。また、社内に専門部署がある場合やプロジェクトが大規模で複雑な場合には、依頼者側が作成するケースもあります。
リニューアルの目的や、ターゲット、コンセプトなどを文章として明確に残すことで、プロジェクトを進めている途中でも振り返って確認することが可能になります。今までの工程が、道順を決めることだとすれば、要件定義書はゴール地点までを記した地図のようなイメージでしょうか。
書面に残すことで、ゴール地点を確認しながら進めることができ、最初に掲げたイメージと完成した時のズレが発生しにくくなります。
作成した要件定義書は、社内外すべての関係者に共有し、共通の認識のもとプロジェクトを進めていくことが大切です。
要件定義書とRFPの違いは?
RFPとはRequest For Proposalの略称で、日本語では「提案依頼書」と呼ばれています。これは、発注側企業が作成してWeb制作会社やシステム開発会社へ提出する文章です。RFPではWebサイトを制作する目的や解決したい課題、実装したい機能やデザインの要望、期日や予算など、条件や要望をまとめます。
制作会社を選定する際に作成したRFPを利用することで、同じ条件での提案を受けられるため、比較検討しやすくなります。
要件定義書に入れる項目
それでは最後に、要件定義書に入れる項目について確認していきます。「こういう項目を入れると分かりやすくなる」というものをご紹介していくので参考にしてみてください。
Webサイト制作の要件定義書に入れておきたい一般的な項目は以下になります。(※プロジェクトの種類や規模に応じて適切なものを選択)
<要件定義書 項目例>
- 背景・目的
- プロジェクト概要
- 各工程のスケジュール・予算
- サイト構成
- デザイン・UX要件
- システム要件
- 技術要件
- インフラ要件
- セキュリティ要件
- リリース要件
- 保守・運用要件
それぞれ確認してきましょう。
背景・目的
まずは、Webサイトを制作するに至った背景や目的を記述します。洗い出した課題や現状の分析結果、Webサイト制作によって達成したい目標、プロジェクトの全体像などを明確にしましょう。
<具体例>
- 現状と課題や分析結果
- なぜWebサイトを制作するのか(目的)
- 具体的なKGIやKPI
- ターゲットやユーザー
- プロジェクトの全体像(制作規模、リニューアル範囲など)
プロジェクト概要
続いて、プロジェクトの概要を記述します。ここでは、制作期日や全体の大まかなスケジュール、人員体制などを明確にします。プロジェクトの全体像が伝わるようにするのがポイントです。
<具体例>
- 人員体制(関係者・チーム構成など)
- 各工程のスケジュール(全体像)
- 定例ミーティングの日程
- 成果物の種類や納品場所(外注する場合などに必要)
スケジュール詳細や各工程の予算
さらに、フェーズや工程ごとのスケジュールをできる限り詳細に明確にします。Webサイトの公開日から逆算し、現実的な日程で組むようにしましょう。また、各工程でかかる費用や予算についても記述しておくと安心です。
サイト構成
どういうWebページが必要なのか、各ページがどのような流れで遷移していくのかなど、サイト全体の構成(サイトマップ)を作成し、ページごとの役割も明確にします。
<具体例>
- サイトマップ
- ページタイトル
- カテゴリ
- ディレクトリ構造
- ディスクリプション
- 各ページに掲載する内容
- 対象OSや対象ブラウザ
大規模なWebサイト制作の場合は、この部分の情報量が非常に多くなるため、要件定義書とは別資料で作成される場合もあります。
デザイン・UX要件
ターゲットに合わせたデザインコンセプトや、ユーザービリティ(使いやすさ)についての要件をまとめます。Webサイトに訪れたユーザーにどういう体験を提供したいかなども明確にします。
<具体例>
- デザインコンセプト
- デザインの雰囲気やイメージ(配色やテイストなど)
- トンマナ(統一するルールなど)
- ユーザービリティの面で重要視したいこと
システム要件
取り決めたUXやUIの要件をもとに、実装する機能を明確にします。たとえば「ユーザーがスムーズに欲しい情報までたどり着くための機能」には「パンくずリスト」や「メニューバー」などを作るなど、ユーザーの体験を実現するための機能を整理していきます。
また、サイト全体に共通で表示する要素はどれか、利便性を意識して実装したい機能は何か・・・などをまとめていきます。
さらに、機能面だけでなく、直接ユーザーが目にすることはない「非機能要件」の明確化も大切です。
たとえば、サイトのページ表示速度を考慮した要件、常にサイトを閲覧できる状態にするための要件など、快適に利用できるようにするための裏側のシステム要件についてもまとめておくと安心です。
<システム要件 まとめの例>
| 実装したい機能要件の種類 | 実装したい機能やページ |
|---|---|
| ページ表示 | ・商品詳細ページ ・記事一覧ページ ・導入事例ページ ・採用ページ |
| 共通要素 | ・ヘッダー/グローバルナビ ・パンくずリスト ・サイト内検索 ・通知バー |
| ユーザー体験(UX) | ・お問い合わせフォーム ・カート機能 ・パーソナライズ表示 |
| 非機能要件 | ・常時SSL ・バックアップ体制 ・2段階認証などの認証強化 ・アクセス解析ツール導入 |
技術要件
Webサイトを制作するうえで、どのような技術が必要かの要件を記述します。
<具体例>
- サーバーやデータ管理システム(実装ミドルウェア)
- 開発言語
- 通信プロトコル
- ソフトウェアフレームワーク(使用する技術)
- バージョン管理
- システム連携方法(既存システムとの連携がある場合)
インフラ要件
Webサイトが運用されるサーバーやネットワークといったインフラ周りの要件を明確にします。具体的には、ドメインやサーバーの選定、バックアップ体制やデータベースの設定といったWebサイトを存在させるためのインフラ基盤について記述していきます。
サーバーやドメインの取得を、依頼者側と制作会社側のどちらがおこなうのかを明確にしておくことも大切です。
セキュリティ要件
Webサイトを安全に運用するための、セキュリティ要件も大切です。サイトで取り扱う情報の機密性に応じて、必要な対応を取捨選択しましょう。
<具体例>
- 漏えい対策(SSL対応・IP制限など)
- システムダウン防止策(DDoS攻撃対策などへの対策)
- セッションタイムアウト
- ユーザー情報の保護(二段階認証の導入など)
- データベースの情報保護(情報の暗号化など)
リリース要件
Webサイトを公開(リリース)する際の要件も明確にしておくと安心です。
<具体例>
- 実行担当者
- 開始日時(期間限定サイトの場合は終了日時も)
- 合否担当者(リリースの最終的な承認者)
- リリースする端末
- リリースの手順
保守・運用要件
Webサイトを公開したあとの運用体制や、保守体制についての要件を記述します。
たとえば、運用体制であれば「今後のコンテンツ更新の頻度や更新するコンテンツの種類」、保守体制であれば「不具合があった場合の対応フローやメンテナンスの方法」などが挙げられます。とくに外部にWebサイトの制作を依頼する場合はサポート範囲や相談窓口・連絡先情報なども明確にしておきましょう。
まとめ:どこに向かって誰が何をどのように対応するのかを明確にしよう
今回は、Webサイト制作における要件定義について解説しました。
「このプロジェクトはどのような目的で進めるのか」「どの項目を誰が担当するのか」「スケジュールや予算はどうなっているのか」「どういう方法で制作していくのか」・・・・などなど、さまざまな「これってどうなる?」というポイントを明確にしてまとめるのが要件定義の役割です。
Webサイトは多くの関係者が協力し合って制作するものなので、皆が同じ目標に向かってプロジェクトを進めるためにも要件定義は大切になります。ぜひ、今回ご紹介した内容も参考にしつつ、プロジェクトに合わせた要件定義をおこなってみてくださいね。
名古屋市のホームページ制作会社 WWG(ダブル・ダブル・ジー)は、お客様のご要望をとことん親身にお聞きし、ユーザーに想いを届けるホームページを制作しています。また、ホームページ公開後のサポート体制も整えています。
もし「ホームページを作りたいけど、どこに依頼したらいいか分からない」ということがあれば、お客様のご要望に合わせてご提案が可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください。
▼その他のWeb制作「戦略・企画」に関するお役立ち情報(記事一覧)は下記の記事からご確認いただけます。
関連記事
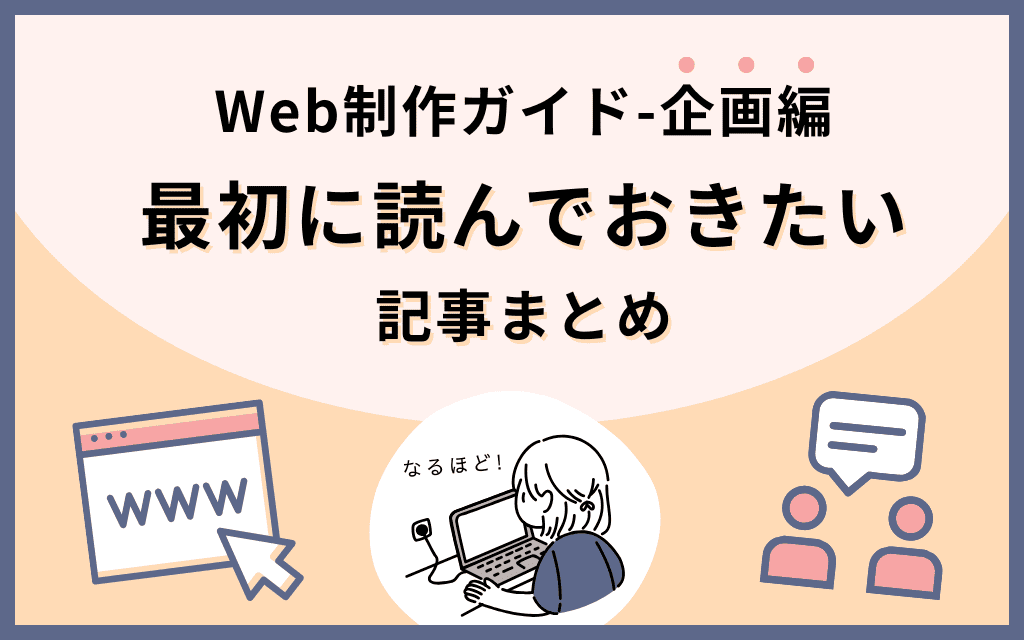
【Web制作ガイド-企画編】最初に読んでおきたい記事まとめ
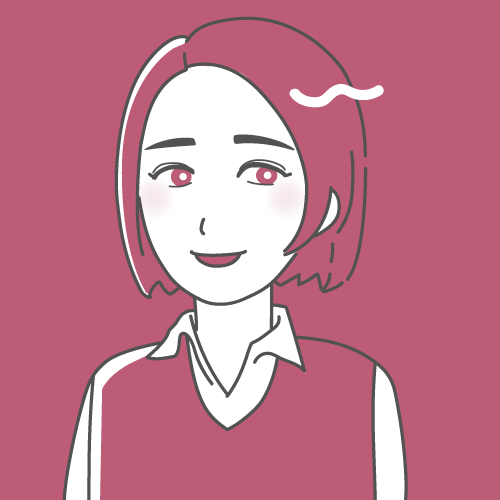
WWGのブログ記事作成専門チームに所属するWebライターです。ホームページ制作やWeb・AIに関することをはじめ、デザイン・コーディング・SEO・人材採用・ビジネス・地元についてのお役立ち情報やニュースを分かりやすく発信しています。【最近のマイブームはChatGPTと雑談をすること】
この人が書いた記事をもっと見る
おすすめ記事のご紹介
-
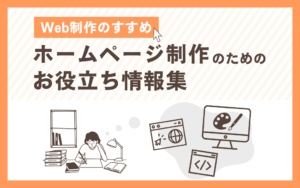
【Web制作のすすめ】ホームページ制作のためのお役立ち情報集
-
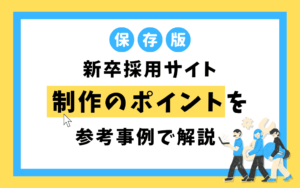
【保存版】新卒採用サイト制作のポイントを参考事例で解説
-
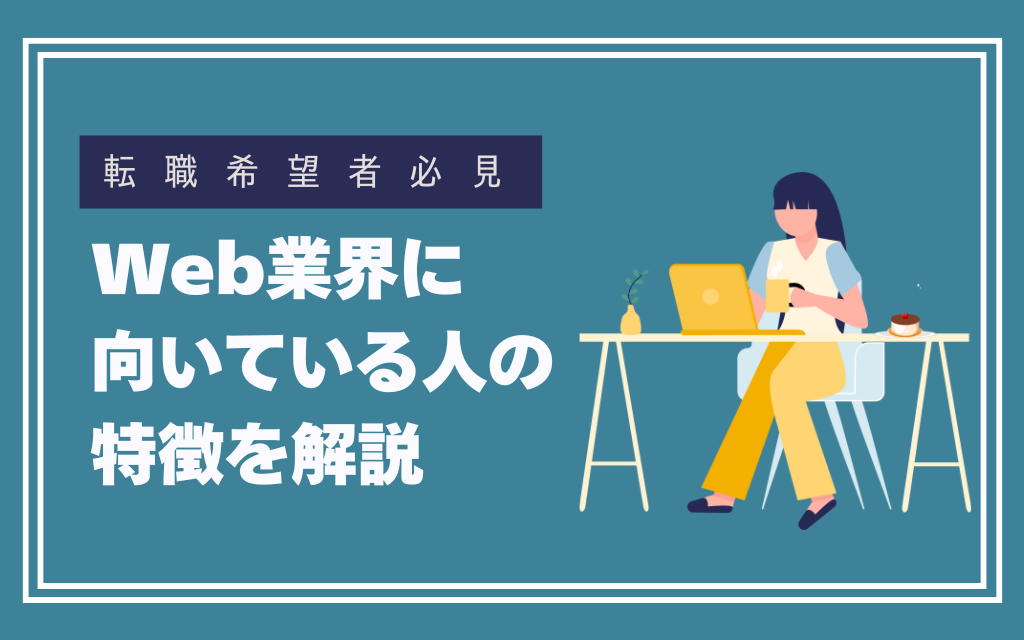
Web業界に向いてる人の特徴とは?ホームページ制作会社の社員が解説
-

【2025年上半期】おすすめ記事一覧|Web・AI・デザインの関連情報
-
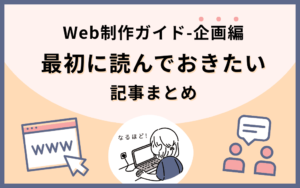
【Web制作ガイド-企画編】最初に読んでおきたい記事まとめ
-
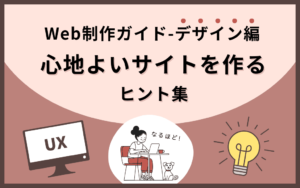
【Web制作ガイド-デザイン編】心地よいサイトを作るヒント集
-
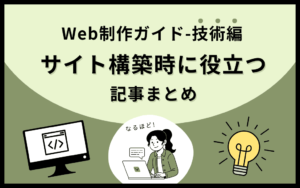
【Web制作ガイド-技術編】サイト構築時に役立つ記事まとめ
-
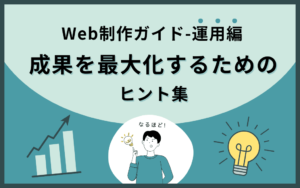
【Web制作ガイド-運用編】成果を最大化するためのヒント集
-
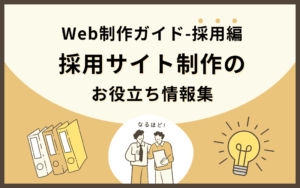
【Web制作ガイド-採用編】採用サイト制作のお役立ち情報集
-
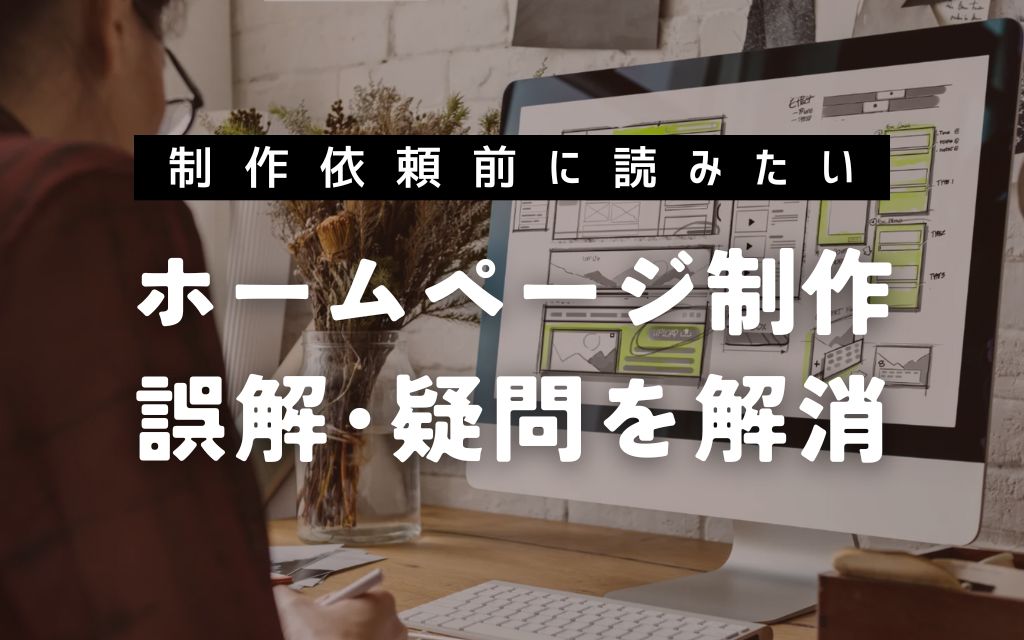
ホームページ制作の依頼前に読みたい、誤解や疑問を解消するための準備記事
-
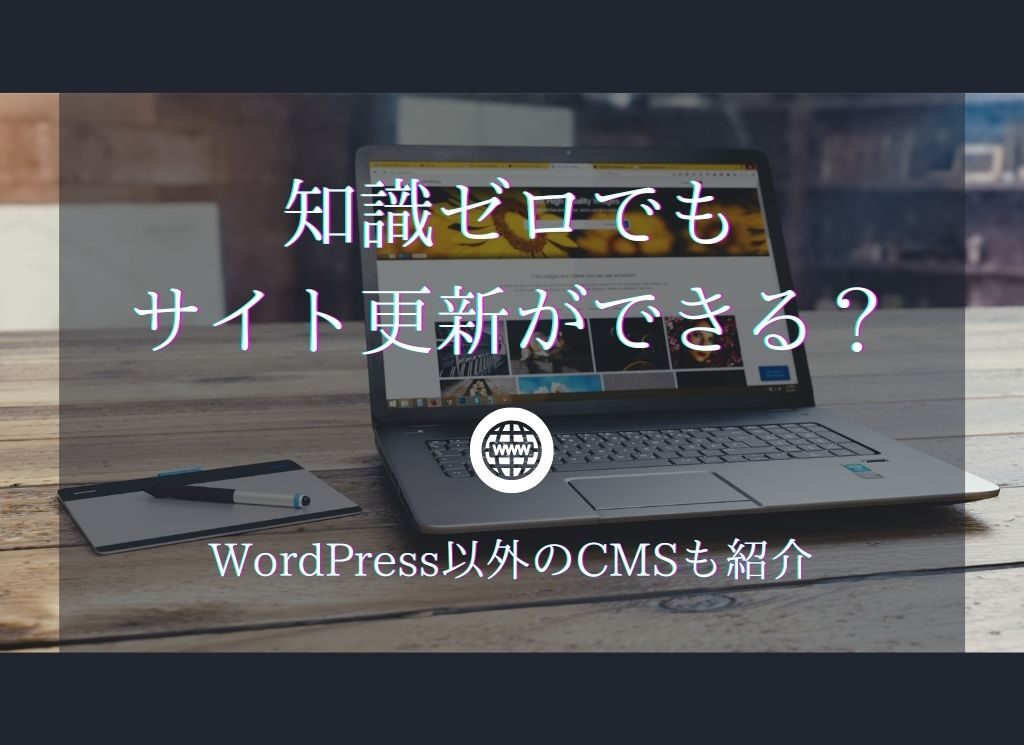
CMSとは?知識ゼロでもホームページを更新できる!?
 WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア
WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア
