お役立ち情報
LPO・EFO・CROそれぞれの意味は?目的・具体例も解説!
良かったら”♥”を押してね!
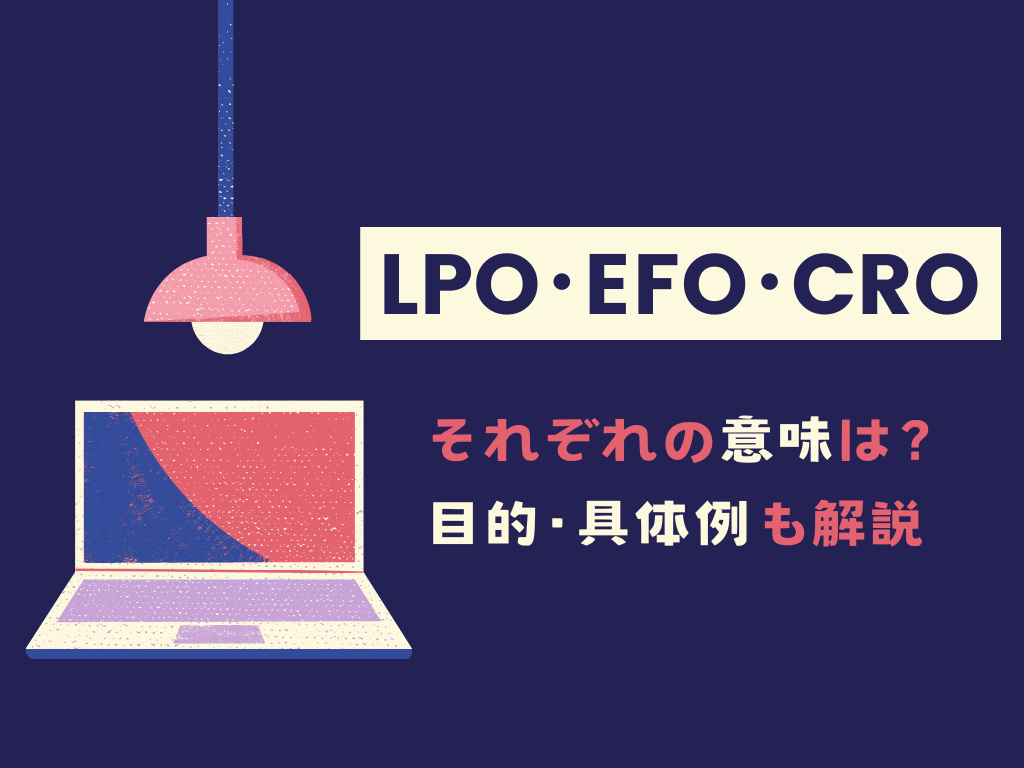
近年、ホームページを運営する人の中では、「SEO」という言葉が浸透しつつあります。
みなさんはご存じですか??
SEO(Search Engine Optimization)は、簡単に言うと、検索エンジンからアクセスを集めるための施策です。
検索エンジンからアクセスをたくさん集められると、そこからビジネスに繋がる可能性が高くなります。そのため、ホームページ運営でSEOは必須だと考えられています。
さて、SEOと似たような言葉に、LPO・EFO・CROがあります。どれもWebサイトを通じて、ビジネスを広げるための概念です。
本日は、LPO・EFO・CROについて詳しく説明していきます!
目次
LPO

LPOとは
LPOとは、Landing Page Optimizationの略で、ランディングページ最適化という意味です。
簡単に言うとLP(ランディングページ)から、購入や問い合わせなどのアクションへ誘導しやすくするための施策を指します。
ちなみに、LPには広義と狭義の意味があります。広義では、ユーザーがホームページにアクセスしたときに、最初に表示されるページのことを指します。
一方、狭義では、Web広告やSNSからのリンク先として設定されるページのことです。特に、サービスや商品をユーザーに購入・問い合わせしてもらうことに特化したページを指します。
LPOでは、主に狭義の意味でのLPを指します。
LPOの目的
LPOは、LPの効果を最大化するために行います。
まず、LPはユーザーを企業の目標に誘導するために運用されます。例えば、分かりやすい例で言うと「商品購入してもらう」「サービスに関する問い合わせをしてもらう」「資料請求してもらう」などが企業の目標になります。
LPOはユーザーを企業の目標に導くために、LPをより効果が出やすい形にしていく目的があります。
LPOの具体例「見込顧客を引き込みやすい構成にする」

LPOの具体例を何例か挙げてみます。
まずは、見込顧客を引き込みやすい構成にしましょう。
LPは、広告やSNSからサービスや商品に興味を持った見込顧客がアクセスします。その層に訴求できるデザインや内容を盛り込むことが大切です。
例えば、中高年向けの化粧品を販売するためのLPだったら、ポップなデザインよりも高級感のあるデザインの方がいいですよね。文章についても、元気さを押し出すより、落ち着いた印象を出す方が商品のイメージに合っています。
このように、ターゲット層をしっかり分析して、LPを作る必要があります。
LPOの具体例「ファーストビューを工夫する」
次に、ファーストビューを工夫することが大切です。ファーストビューとは、サイトの中でユーザーが最初に目にする部分のことです。
先ほども書きましたが、LPには商品やサービスに興味を持っているユーザーがアクセスします。
せっかく興味を持ってくれているユーザーがパッとサイトを見ただけで直帰してしまったらもったいないですよね。
なので、ファーストビューとなる部分にインパクトのある画像やキャッチコピーを持ってきたり、目を引く色彩構成にしたりして、ユーザーを引き留めるようにしましょう。
LPOの具体例「テスト検証する」
LPの効果が出ているかを計測するために、テスト検証をすると良いでしょう。
テストの方法はいろいろあり、その一つにABテストがあります。
ABテストは、2つ以上のLPを作成して、効果を比較するテストです。
例えば、文章やレイアウトが異なるAサイトとBサイトのどちらが効果的かを調べたり、AサイトとBサイトで申込みボタンの色だけを変えて、その色の違いがどの程度効果に影響を与えるかを検証したりすることができます。
他にも多変量テストでは、見出しや画像、色調などを数取り組み合わせて、どの組み合わせが一番効果的かを測ることができます。
このように、色々なテストでLPの効果について検証し、改善していくことが大切です。
EFO

EFOとは
EFOとは、Entry Form Optimizationの略でエントリーフォーム最適化という意味があります。
エントリーフォームとはWeb上で問い合わせや注文を行う際の入力画面のことです。
つまり、ユーザーがフォームに入力しやすくするための施策のことを指します。
EFOの目的
EFOの目的は、ユーザーを逃さないようにすることです。
問い合わせ画面や注文画面といったエントリーフォームに情報を入力するユーザーは、すでに企業や商品に興味を持っているユーザーです。
しかし、エントリーフォームが使いにくかったら、「面倒くさいから入力するのはやめておこう」という思考になるかもしれません。
そうすると、せっかく関心をもってくれているユーザーを逃してしまうことになり、ビジネス機会を損失してしまいます。
つまり、EFOはニーズを持っているユーザーを獲得するために重要ということですね。
EFOの具体例「レイアウトを見直す」

EFOの具体例をみていきましょう。
まず、レイアウトを見直すことが大切です。ユーザーがストレスなく使えるようなレイアウトを心掛けましょう。
具体的には、ユーザーが入力しやすい配置にしたり、入力項目を絞ったりすると最後まで入力してもらえる可能性が高くなります。
EFOの具体例「最適な表示にする」
デバイスごとに最適に表示されるようにすることも大切です。
例えば、スマートフォンから情報を入力しようとしたときに、パソコン用の入力画面が出てきたら見にくいし、入力しづらいですよね。そこでユーザーが離脱してしまったらもったいないです!
スマートフォン、パソコン、タブレットなどそれぞれの端末に対応したエントリーフォームを提供しましょう。
EFOの具体例「エラーメッセージを表示する」
入力項目に不備があったとき、どこに不備があったのか一目で分かるように表示することも大切です。
どこに不備があるか分からず、探す時間が掛かってしまうとユーザーは離脱しやすくなってしまいます。
不備があった項目欄の近くにエラーメッセージを表示させることで、「ここを直せばいいんだな」と分かりやすくなります。
さらに、文字を大きくしたり、色を変えたりしてエラーメッセージを表示させるとより分かりやすくなりますよね。
CRO

CROとは
CROとは、Conversion Rate Optimizationの略でコンバージョン率の最適化を指します。
コンバージョンとは、企業が特定の目標や行動を達成することです。
Webサイトではユーザーに商品購入や問い合わせなどをしてもらうことをコンバージョンとして設定することが多くなります。
つまり、CROとはユーザーを企業の目標へ誘導するための施策を指します。
この説明を見るとLPOと大体同じに思えますよね。
LPOは特にLPに関する施策を指していて、CROはWebサイト全般に対する施策というイメージです。なので、LPOもEFOもCROの一部という解釈ができます。
ちなみに、コンバージョン率は以下の式で表せます。
コンバージョン率(CVR)=コンバージョンしたユーザー数/特定のページに流入したユーザー*100
例えば、「ユーザーに問い合わせをしてもらうこと」をコンバージョンに設定したとき、100人がページに流入して、1人から問い合わせがあったらコンバージョン率は1%になります。
CROの目的
CROは、Webサイトを通じてコンバージョン率を根本から向上させる目的があります。
例えば、リスティング広告を出稿すれば、コンバージョン率を向上させることはできますが、それはCROとは呼びません。
CROは、長期的にWebサイトの分析・改善を行い、根本からコンバージョン率を向上させるので、広告とはそもそも違ったアプローチです。
つまり、CROは、Webサイトの問題点を改善していくことで、企業の目標を達成しやすくする目的があります。
CROの具体例「CTAの改善」

次にCROの具体例をみていきます。
まず、CTAを見直しましょう。CTAとは Call To Actionの略で、行動喚起という意味です。
例えば、「資料請求はこちら!」「今すぐ会員登録!」などの言葉でユーザーを目的の行動へ誘導するのがCTAです。
こういったCTAの言葉や設置場所を変えたり、カラーやデザインを工夫したりしてコンバージョン率を向上させましょう。
CROの具体例「サイトの読み込み速度を向上する」
次に、サイトの読み込み速度を向上させましょう。
Webサイトの読み込みに時間が掛かってしまうとユーザーは離脱しやすくなる傾向があります。逆に言うと、読み込み速度が早いとコンバージョン率が上がりやすくなるということですね。
ちなみに、SEOの観点からも読み込み速度は速い方がよいでしょう。
サイトの読み込み速度は、画像のファイルサイズを小さくしたり、ソースコードを軽量化したりすることで改善できます。
CROの具体例「LPO・EFOを実施する」
CROとはでも説明しましたが、CROはWebサイトに対する包括的な施策です。
なので、その一部分となるLPO・EFOを行うことで、CROを実施できます。
まず何から始めていいか分からないという方は、LPO・EFOを行ってみるのがオススメです!
まとめ
■LPOは、LPから購入や問い合わせなどのアクションへ誘導しやすくするための施策
■EFOは、ユーザーがフォームに入力しやすくするための施策
■CROは、ユーザーを企業の目標へ誘導するため包括的な施策
全てWebサイトを最適化するための施策ではありますが、それぞれ違いがありましたね。
それぞれの対策を実施したいけれど、自分たちでは難しいという場合は、ホームページの制作会社に相談してみると良いと思います。
当メディア「WWGスペース」は、名古屋のホームページ制作会社 WWG(ダブル・ダブル・ジー)が運営するオウンドメディアです。当社WWGは、ホームページを作るプロとして、IT・Web・AI関連の最新情報に日々アンテナを張って技術を磨いています。WWGの強みは、地域に特化した価値あるホームページ制作です。
今後も、WebやIT、AIに関するお役立ち情報はもちろん、ホームページ制作・Web制作に関する情報も分かりやすくお届けしていきますので、ぜひお楽しみに…!
▼その他のWeb制作「運用」に関するお役立ち情報(記事一覧)は下記の記事からご確認いただけます。
関連記事
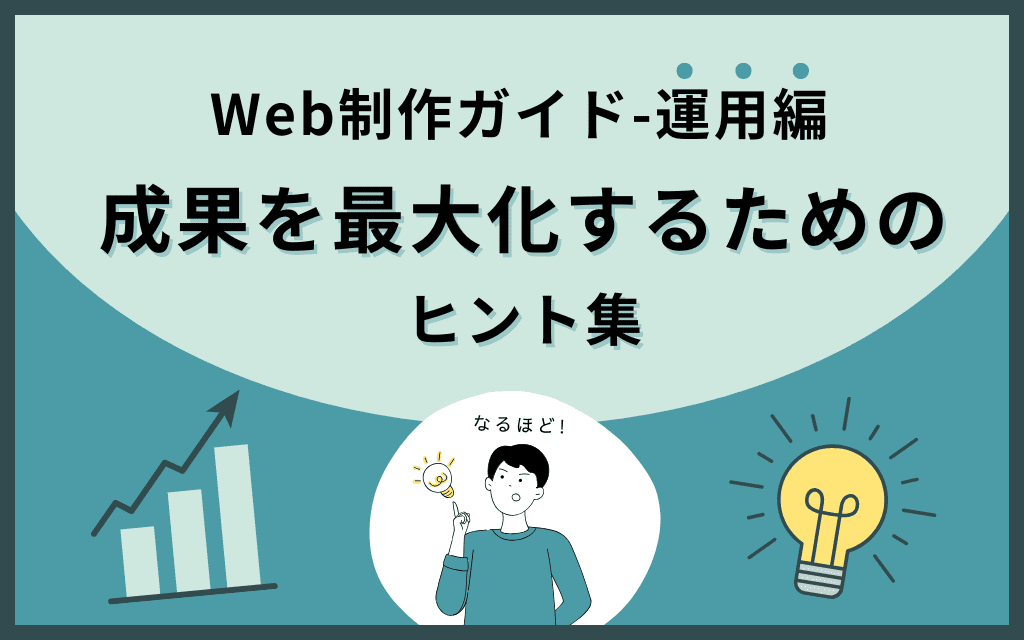
【Web制作ガイド-運用編】成果を最大化するためのヒント集
おすすめ記事のご紹介
-

【初心者向け】ランディングページ(LP)とは?目的や作り方を解説
-
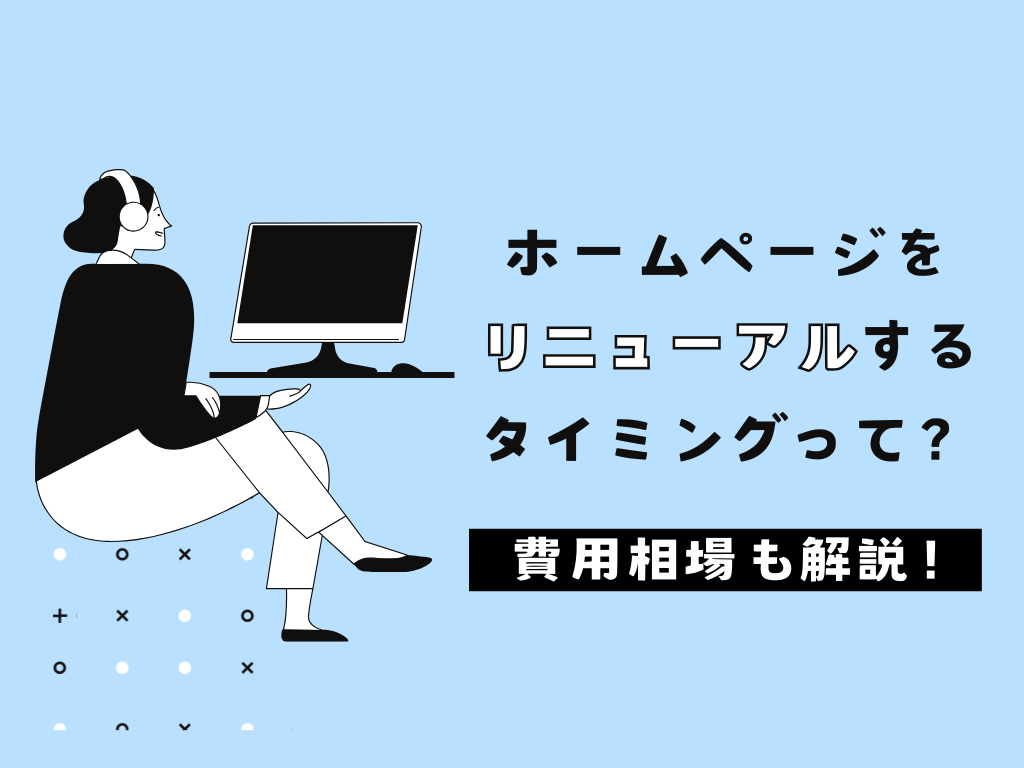
ホームページリニューアルのタイミングは?費用相場も解説!
-
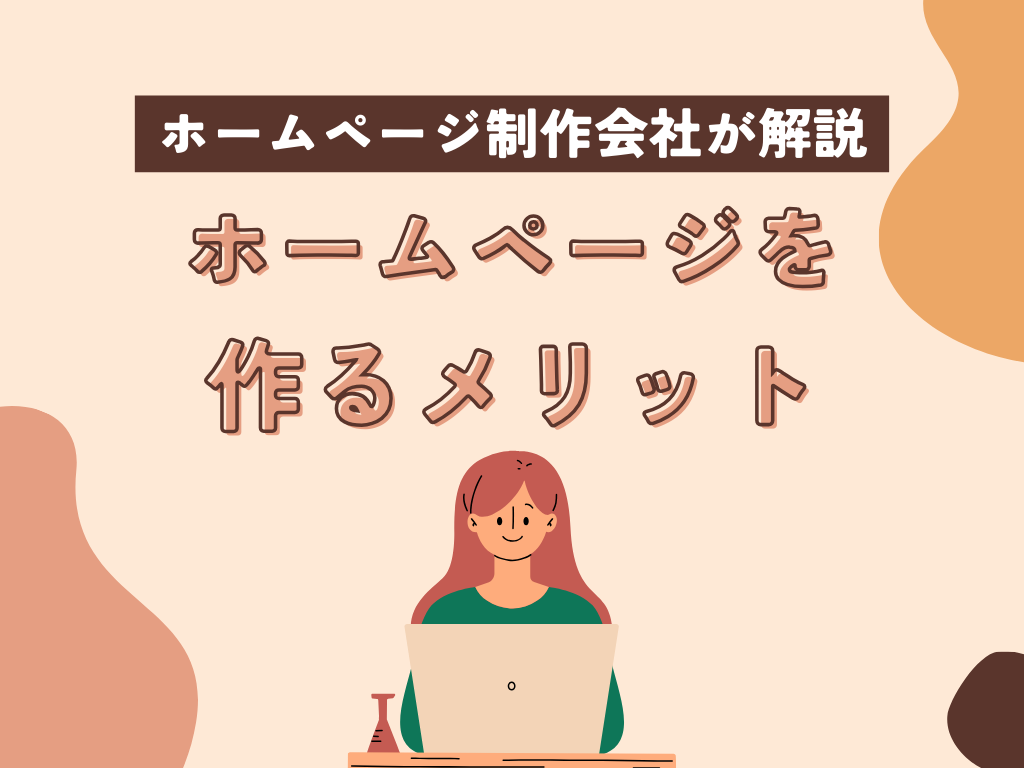
ホームページを作るメリットは?ホームページ制作会社が解説
-
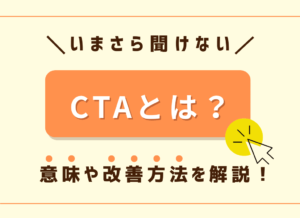
【いまさら聞けない】CTAとは?意味や改善方法を解説!
-
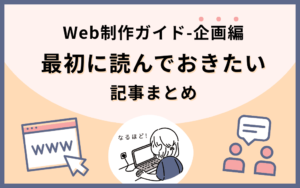
【Web制作ガイド-企画編】最初に読んでおきたい記事まとめ
-
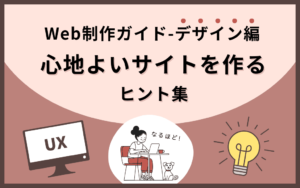
【Web制作ガイド-デザイン編】心地よいサイトを作るヒント集
-
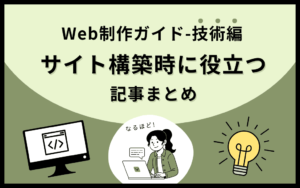
【Web制作ガイド-技術編】サイト構築時に役立つ記事まとめ
-
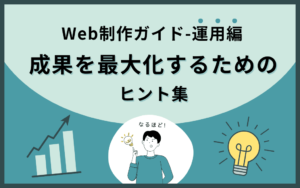
【Web制作ガイド-運用編】成果を最大化するためのヒント集
-
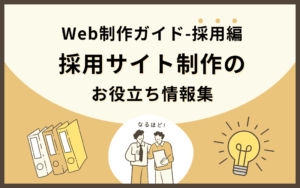
【Web制作ガイド-採用編】採用サイト制作のお役立ち情報集
-
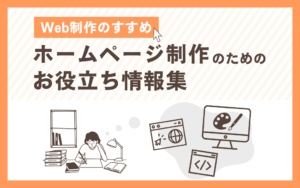
【Web制作のすすめ】ホームページ制作のためのお役立ち情報集
 WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア
WWGスペース 名古屋のホームページ制作会社が発信するオウンドメディア
